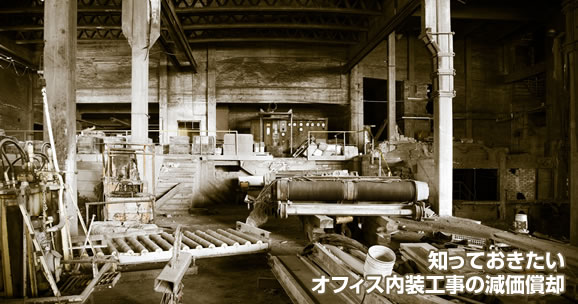
賃貸事務所や賃貸店舗など、事業用として賃貸物件を使用する場合に避けては通れないものとして内装工事があります。
小規模なオフィスは別として、ある程度の規模になれば、ほとんどの企業で内装工事を行うでしょう。その内装工事、デザインや規模、扱う材料によっては大きな費用となりますが、移転の際に資産会計上の処理をどのようにするかを考えておかなければなりません。
最初に掛った費用だけに目を向けていると経営の戦略上にも大きな影響を与えることになりかねませんので注意が必要です。
一度に全額経費にはできない
移転、または既存のオフィスでのレイアウト変更などを行った場合、その時に一度に全額経費として扱えることはほとんどありません。内装工事の価値の減少に応じて、数年かけて減価償却費として計上する必要があります。
現在、平成10年4月1日以降に購入・取得した物の償却方法は、定額法に限られています。
内装工事の減価償却費
減価償却とは設備投資費用を購入した年ではなく、数年にかけて分けて会計の処理を行うことです。
購入金額を一定の期間に分けて費用計上しますので、実際の現金の動きはありませんが、帳簿上で利益が減少するので、節税できるという利点がある一方、赤字になる場合もあるので注意が必要です。
車や製造機械などが代表的な設備投資ですが、オフィスの内装も設備投資にあたりますので、減価償却となります。
耐用年数の決め方
一般的に耐用年数は、合理的な耐用年数によって決まるとされています。
内部造作の耐用年数は、建物の耐用年数(SRC造の事務所で50年)を適用することは事実上そぐわないため、内装自体を一つの資産として、造作の種類や材料、用途から合理的に耐用年数を決めます。
賃貸借契約における内装工事の減価償却
賃貸借契約における内装工事の減価償却耐用年数は、大きく分けると契約の種類によって異ってきます。では、どのように違うのでしょうか。
期間の定めのない賃貸借契約
「期間の定めのない」というのは、契約期間○○年とされていても、その契約が普通賃貸借契約で、満期に更新できるものも含まれます。
この場合の耐用年数は、前述したとおり、造作の種類や材料、用途などによって合理的に見積もるものとされています。一般的なオフィスの場合の内装工事の耐用年数は、だいたい10年~15年くらいで減価償却されます。
期間の定めがある賃貸借契約
賃借期間の定めがあり、契約期間の更新ができない場合で、有益費の請求もしくは買取請求をすることができないものについては、賃借期間を耐用年数とすることができます。
分類することで節税できることも
オフィスの内装工事は、什器、備品なども含めてまとめて耐用年数を決めることがよくありますが、実は、面倒かもしれませんが工事の内容によって分類することが望ましいです。
分類することで、内容ごとに科目と金額が算出でき、耐用年数も決められますので、全体でまとめて計上するよりも、早くて多くの経費を計上することができます。
最後に
内装工事の減価償却については、場合によって異なり専門的な知識分野でもありますので、詳細まで踏み込んだ解説は控えさせていただきました。ここでは、内装工事は減価償却費として計上でき、耐用年数はどれくらいなのかをご理解いただければと思います。
また、冒頭でも述べたように、費用の算出は経営戦略にも関わる大事な項目でもありますので、実際に内装工事の減価償却、耐用年数については、専門的な税理士や会計士と御相談の上、慎重に判断していただきたいと思います。



Leave Your Response